「平和」と聞くと、多くの人が「戦争がない状態」や「穏やかな社会」を思い浮かべます。
一方で「無関心」もまた、争いを避ける姿勢のように見えることがあります。
しかし実際には、この2つはまったく異なる概念です。
本当の平和は、“関心と行動の上に成り立つ積極的な状態”であり、
無関心はむしろ「静かな暴力」として社会を冷たくしていきます。
1. 「平和」とは ― 行動と尊重が支える“積極的な状態”
「平和(peace)」とは、単に戦争がないことではなく、
人と人が互いを尊重し、安心して共存できる“積極的な状態”を指します。
ノルウェーの社会学者ヨハン・ガルトゥング(Johan Galtung)は、
「積極的平和(Positive Peace)」という概念を提唱しました。
それは、貧困・差別・構造的不平等といった“見えない暴力”をなくし、
誰もが尊厳をもって生きられる社会を目指す考え方です。
つまり、平和とは“静けさ”ではなく、
互いの違いを受け入れ、行動によって尊重を示す状態なのです。
2. 「無関心」とは ― 問題から目をそらす“責任の放棄”
「無関心(indifference)」とは、文字通り“関心を持たないこと”。
心理学的には認知的回避(cognitive avoidance)と呼ばれ、
ストレスを避けるために問題を見て見ぬふりをする防衛反応とされます。
一見、「波風を立てない」ように見えますが、
無関心が広がると社会には次のような弊害が生まれます。
- 不正や差別を「自分には関係ない」と見過ごす
- 他人の苦しみに鈍感になり、共感力が低下する
- 問題が“見えないまま”拡大していく
誰も直接手を下していないのに悲劇が起きる――
それが、現代社会における“静かな暴力”なのです。
3. 「平和」と「無関心」の違い
| 観点 | 平和 | 無関心 |
|---|---|---|
| 心の向き | 他者への尊重と関心 | 自己保身と無視 |
| 行動 | 対話・協力・助け合い | 放置・沈黙・距離をとる |
| 感情 | 共感・思いやり | 無感情・鈍化 |
| 社会への影響 | 信頼と安定を育む | 分断と孤立を生む |
平和は「関心の結果」から生まれ、無関心は「関心の欠如」から生まれる。
わずか一文字の違いですが、その本質は正反対です。
4. “静かな暴力”とは ― 道徳的無関与のメカニズム
無関心は直接的な暴力ではありませんが、
「助けられたはずの人を放置する」という形で間接的な暴力となります。
心理学者アルバート・バンデューラ(Albert Bandura)は、
これを「道徳的無関与(moral disengagement)」と定義しました。
人は「自分の責任ではない」と思うことで、他人の苦しみに鈍感になります。
たとえば、次のような場面です。
- SNSでいじめを見てもスルーする
- 職場でハラスメントを見ても「関わりたくない」と黙る
- 災害時に困っている人を見ても「誰かが助けるだろう」と思う
こうした“沈黙の選択”の積み重ねが、社会を冷たくしていくのです。
5. 現代社会における「無関心の構造」
現代は、情報があふれる「刺激過多社会」です。
ニュース、SNS、広告、動画──次々と流れる情報の中で、
人は「共感疲労(compassion fatigue)」を起こしやすくなっています。
また、心理学者ジョン・ダーレイとビブ・ラタネが提唱した
「傍観者効果(bystander effect)」も関係しています。
多くの人がいる場面ほど、「誰かが助けるだろう」と思い込み、行動が遅れるのです。
つまり、現代の無関心は“環境によって助長される社会的現象”でもあります。
6. 平和を守る“関心の力”
では、私たちはどうすれば「平和=関心ある状態」を保てるのでしょうか。
そのカギは次の3つです。
- 共感(Empathy)を意識する
他人の立場を想像し、「自分だったらどう感じるか」を考える。 - 声を上げる勇気を持つ
不正や不公平を見過ごさず、小さくても発信する。 - 行動に移す
寄付・ボランティア・シェアなど、関心を“形”にする。
たとえ小さな行動でも、それが連鎖すれば「積極的平和」は確実に育ちます。

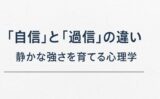
7. まとめ|無関心は“平和の最大の敵”
「平和」と「無関心」は、どちらも静けさを伴うため見分けがつきにくいものです。
しかし、本当の平和は“静けさの中にぬくもりがある状態”であり、
無関心は“静けさの中に冷たさがある状態”です。
社会を変えるのは、声の大きな人ではなく、
関心を持ち続ける静かな人々です。
平和とは、「見て見ぬふりをしない勇気」そのものなのです。
📝 出典・参考文献
- Encyclopaedia Britannica:「Peace(平和の定義)」
- United Nations:「Peacebuilding(平和構築の取り組み)」
- American Psychological Association:「Stress in America Survey 2022(社会と無関心の関係)」
- UC Berkeley Greater Good:「Empathy(共感の定義)」
- The New York Times:「The Bystander Effect(傍観者効果)」
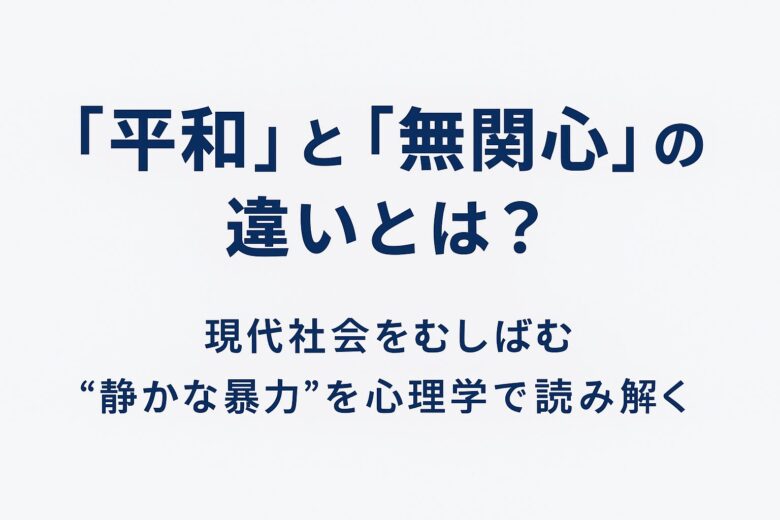


コメント