「情けは人のためならず」ということわざは、日常会話でも耳にしますが、多くの人が誤解して使っている表現のひとつです。私自身も若い頃に「人に情けをかけるのはその人のためにならない」という意味だと勘違いし、上司に訂正された経験があります。本記事では、このことわざの本来の意味や使い方を整理し、正しく理解できるように解説します。
「情けは人のためならず」とは
「情けは人のためならず」とは、「他人に親切を施すことは、やがて自分に良い形で返ってくる」という意味を持つことわざです。
しばしば「人のためにならない」と誤って解釈されますが、本来は逆に「思いやりは巡り巡って自分を助ける」という教えを示しています。
由来
この表現は江戸時代以前から広く用いられてきました。「情け」とは、人を思いやる心や親切心を意味します。つまり「人への思いやりや善行は、巡り巡って自分の利益や幸福に繋がる」という人生訓を表したものです。
使用シーンの例
- 困っている同僚を助けたときに「情けは人のためならず、きっと自分に返ってくる」と励ます
- 子どもに「親切を大切にしよう」と伝えるとき
- ビジネスシーンで協力や助け合いを促す際の言葉として
実際に私自身も、かつて同僚の資料作成を手伝ったところ、後日その人が別のプロジェクトで力を貸してくれました。この体験から「情けは人のためならず」という言葉の真意を深く実感しました。
誤解されやすい意味
現代では「人に情けをかけても、その人のためにならない」という誤用が非常に多く見られます。
実際に文化庁が実施した「国語に関する世論調査」でも、多くの人が本来の意味を誤解していることが明らかになっています。
出典:文化庁「国語に関する世論調査」
(https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/kokugo_yoron/)
「情けは人のためならず」の例文
- 「彼に協力してあげよう。情けは人のためならずだ。」
- 「地域清掃に参加するのは、情けは人のためならずという考えからだ。」
- 「困っている人を助けることは、情けは人のためならずだと教えたい。」
誤用に注意すべきポイント
- 「人のためにならない」という意味ではない
- 「親切は無駄」という解釈は誤り
- 教育・指導の場では特に、正しい意味を添えて説明することが大切
ビジネスシーンでの使い方と注意点
「情けは人のためならず」は誤解されやすいため、ビジネスの場で使用する際には細心の注意が必要です。
特にメールや会議などのフォーマルなシーンでは、誤ったニュアンスで受け取られないように工夫しましょう。
- 「助け合いの精神」を強調したいときに用いると効果的
- 誤解を避けたい場合は「親切は自分に返ってくる」と具体的に言い換える
- 研修や教育の場では、ことわざの解説を添えて使うと誤用防止につながる
類義語・関連表現との比較
「情けは人のためならず」と同様に「善行は巡り巡って自分に返ってくる」という考えを持つ表現は複数存在します。
これらを理解しておくことで、場面に応じた適切な言い換えが可能になります。
| 表現 | 意味 | 使用例 |
|---|---|---|
| 因果応報 | 善悪を問わず、行いは必ず自分に返ってくる | 「彼の成功は因果応報だと思う」 |
| 善因善果 | よい行いはよい結果を生む | 「善因善果を信じて日々努力する」 |
| 情けは巡る | 親切は巡り巡って返ってくる | 「情けは巡るという考えで地域活動に参加する」 |
関連記事
まとめ|「情けは人のためならず」を正しく理解しよう
- 本来の意味は「情けは巡り巡って自分に返る」という前向きな人生訓
- 「人のためにならない」という解釈は誤用なので注意
- ビジネスでも日常生活でも、人とのつながりを深める知恵として使える
このことわざを正しく理解すると、人との関わり方が少し優しく、そして前向きになります。
親切にしたことがすぐに返ってこなくても、いつか思わぬ形で自分を助けてくれることがある――そんな希望を持たせてくれる言葉です。
ぜひ明日からの会話や文章に取り入れて、周囲との関係づくりに役立ててみてください。


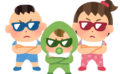
コメント